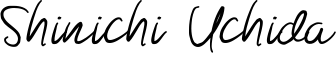おざわ・つよし
おざわ・つよし1965年、東京都生まれ。都市の片隅など各所に地蔵画を設置する『ジゾーイング(地蔵建立)』シリーズ、世界各地で地元野菜を使った武器を作り、現地女性が構えた姿を撮影後、皆で食べてしまう『ベジタブル・ウェポン』シリー ズ、架空の伝統画法による「醤油画資料館」など、ユーモアと批評性をたたえた作品を展開する。アーティストグループ「昭和40年会」や、中国の陳劭雄(チェン・シャオション)、韓国のギムホンソックとのアートユニット「西京人」の活動も行う。
http://www.ozawatsuyoshi.net/
取材・文:内田伸一 ポートレート:名和真紀子
雑誌ART iT (アートイット) 22号(2009年冬/春号)
牛乳箱の中の小宇宙から、布団をうずたかく積み上げた遊技場的作品まで、多様なスタイルとスケールで幾多の国際展を飛び回る旅人のようなアーティスト。その経験から語る、作家と展覧会、そしてキュレーターとの関係とは―― 。

Everyone Likes Someone As You Like Someone, 2006–2008
Installation view at "Akasaka Art Flower 08," 2008 Photo Kato Ken

The Seven Wonders of Kanazawa
Installation view at "Kanazawa Art Platform," 2008
―― 小沢さんは常に世界中で多くの展覧会に参加している印象があります。2008年はいくつの展覧会に参加したのでしょう。
今日の取材主旨を聞いて、試しに展覧会リストを作ってみました。08年は18件でしたね。初展覧会を経験した1992年以来、いちばん多かった。自分の活動の証ということで、制作と同じくらい展覧会参加は重要です。自分ではコマーシャルな作家ではないと思っていて、その意味でも大きな存在ですね。
―― 活動の初期から続く『なすび画廊』シリーズは、展覧会空間に対する批評でもありましたね。意外な場所に現れる小さな牛乳箱と、その中に展開された「画廊」は、世界一小さな展覧会とも言えそうです。


Nasubi Gallery
Left: guerilla style installation at The Ginburart project 1993 (milk box tied to tree) Photo Anzai Shigeo
Right: exhibition view at Cities on the Move (1997, Vienna Secession)
Courtesy the artist and Ota Fine Arts
始まりは93 年の『ザ・ギンブラート』という企画です。当時若手の作家たちが呼びかけ合い、銀座の路上で作品をゲリラ発表しました。その一帯に多い「貸画廊」(編注:自らは企画展を行わず、展覧会を開きたい作家に有料でスペースを貸し出すギャラリー)への批判と、純粋に自分のスペースが欲しいという問題意識とが結びついた表現です。当時のドキドキ感や「どんな方法でも見せたい!」という志は持ち続けていたい。厳密に言えば、道路交通法に違反してたらしいですけど(笑)。
―― その『なすび画廊』へ他の作家さんを招いたり、最近では架空の研究者の姿を借りた展覧会(岡本七太郎企画展『はちみつと極東と美術』、07年)を行ったり、小沢さん自身、キュレーション的な表現も試みています。展覧会の現場では作家とキュレーターが同じ目的を共にするわけですが、両者の関係性はどう考えますか。
もちろん基本的な役割が違うし、それ以外でも言語能力や、お金を集めて上手に扱う力とか(笑)、得てして作家が苦手な分野でも彼らは力を発揮してくれるわけですよね。でも、アートを愛する熱量は同じくらいある、そうあってほしいと思っています。それと、展覧会って動員数や評判は作家が定点観測できないから、展覧会関係者がその窓になってくれる感じもありますね。
キュレーターとの展覧会づくり
―― 展覧会のプラン作成では、小沢さんも細部にまでかなり参加しますか。
そうですね、できるだけ「自分の空間」にしたいので。初めの内はゲリラ展示や、街中の店舗の一角とかでやっていたけれど、あるときから典型的な美術空間、つまりホワイトキューブでばかりやるようになりました。すると、とりあえず壁に何か掛ければどうにかなる。それは一種の魔法だけど、それだけじゃつまらない。一方、以前のセザンヌらのサロン時代なんかは、美術館もギャラリーも白い壁じゃなかっただろうし、絵を縦に数段掛けとか……それはそれで、空間全体のことはあまり気にかけなくてよかったのではと思うんです。作家としてそこをどう考えるべきか、モヤモヤしていた時期がありました。
――途中で何か解決策や、気づいたことがあったのでしょうか。
僕にとって決定的だったのは、侯瀚如(ホウ・ハンルゥ)とハンス・ウルリッヒ・オブリストがキュレーションした『Cities on the Move』展(97 年〜)への参加です。これは世界各都市を巡回し、行く先々でコールハ―スや坂茂など個性派建築家が独自の会場構成を行います。僕は『なすび画廊』シリーズを20〜30個くらい出展しました。毎回会場に出向き、自分でその空間を読み込んで、これはという場所を侯瀚如に示して設置して回る。隙間みたいな場所もあえて使ったし、展覧会をくまなく観るわけです。それがすごく刺激的で、展示というものを学んだ気がする。
―― 侯瀚如については、どんなところを評価しますか。
彼が持つ「ぐちゃぐちゃのダイナミズム」が好きですね。混沌の先に何かを見ているようでもあるし、常に問題意識を持って何かに立ち向かっている緊張感がある。そしていつも、アートでできることを探す姿勢でいる。それは僕も常に考えていることなので、共感できます。
―― そうした経験は後の活動、例えば森美術館での大規模個展『同時に答えろYesとNo!』(04年)などでも活かされたのでしょうか。キュレーターは片岡真実さんですね。

Tonchiki View House, 2004
Installation views at "Ozawa Tsuyoshi: Answer with Yes and No!," 2004
Photo Sakurai Tadahisa Courtesy Mori Art Museum

Sharaku Work, 1996/2004
Installation views at "Ozawa Tsuyoshi: Answer with Yes and No!," 2004
Photo Sakurai Tadahisa Courtesy Mori Art Museum
『Cities on the Move』で自分なりに考えたのは、20世紀がホワイトキューブの時代だったとしたら、21世紀に自分はその白壁から脱却すべきではないかな、と。だから『同時に〜』展では、自分に与えた課題がそれこそ「壁を使わない」でした。壁を使ったのは『なすび画廊』の展示のみで、これは路上から生まれた作品だから逆によいだろうと。全体の会場構成から、自分で模型などを作って参加しました。僕の作品はけっこうスタイルがバラバラだから、いかにつながりや分類を上手く表現するかで悩みましたが、片岡さんとはすごく仕事をしやすかった。作家のリクエストや提案を真摯に受け止めてくれるから。
―― ダンスの珍しいキノコ舞踊団や、音楽の大友良英など、異ジャンルの表現者を招いたイベントも開催されました。
僕の作品の多くは、どこかステージみたいな要素もあって、実際に展覧会で何かできたらというのはもともと自分の中にあったんです。片岡さんから、会期中何かイベントをやろうかと話があって、ならばクロスジャンルがいいなと思って。
美術家から見たキュレーションの意義
―― 観衆のための、よい展覧会づくりの技術についてはどう考えますか。例えば、見やすい、身体に入ってきやすい展示構成など。
視覚的によくできた展示というのは、それこそキュレーターのセンスに依るところが大きいのでは? 例えば『笑い展 : 現代アートにみる「おかしみ」の事情』(07年、キュレーターは片岡真実)は、50名あまりの作家が参加したので、会場構成が相当重要だった。グループ展の魅力は、作家同士が同じスペースの中で表現を競い合い、逆に皆でひとつの美しい空間を造る意識も同時に起こるところ。でも、ある程度込み入ってくると、作家も自分のことに集中してしまいがちになる。キュレーションの力が発揮されるのはひとつ、そんな局面かもしれません。そう考えると、そういうセンスは比較的、グループ展で強く出るのかな。さらに国際展のように巨大になると、会場選びから大仕事ですよね。

Chen Shaoxiong + Ozawa Tsuyoshi GUANGDONGTOKYO3, 2006–07
Installation view at "All About Laughter: Humor in Contemporary Art," 2007
Photo Watanabe Osamu Courtesy Mori Art Museum
―― もうひとつ、展覧会の重要な要素に図録もあると思います。収録されたキュレーターらの論文を読んで、納得したり、ときには認識のズレを感じたりすることもあるのでしょうか。
著しく的外れだと困るけれど、アート作品っていろいろに解釈できるものですから、そういう見方もあるのかと思うくらいです。一方、作家にもよるけれど、キュレーターの思惑の足をすくってやれ、という挑戦的な参加方法もあっていいのかもしれない。ジャーナリズムから見ると、明確に統一された見解が欲しいと思うのもわかりますが、僕はあまり気にしません。
―― 最後に、作家から見た、よいキュレーターとは?
うれしいのは…… 作家を信頼してくれて、わがままにも付き合ってくれる人。なんて言うと子供みたいですが(笑)、もちろん全肯定でなくていいんです。逆に「これだけ? もっとやろうよ」と挑発してくれる人とか。とにかく、何事にも真剣に対応してくれる人ですね。苦手なのは、なぜか上から目線だったり、「不幸にも君と組んじゃったから仕方なくやってるんだよ」「ウチは本来はこういう系統じゃないんだけど……」みたいなタイプかな。
―― 作家とがっぷり四つでぶつかり合う熱い人、自分のビジョンを推し進める人、逆に自分の考えをあまり表に出さない人などなど……いろいろですかね。
そうそう。作家が「ここは自分たちでやれる!」と思うようなときは、そこは任せて、必要な調整に徹してくれる人もいます。当たり前だけど個々のケースにもよるわけで。例えば、欧米はアジアより歴史や経験があるぶん、展覧会作りも優れている、とも一概に言えないというか……ヨーロッパでもルーズなお国柄の場所があったり、アジアも様々ですよね。さらに美術館ごと、キュレーターごとの個性もあります。作家としてそこにどう関わるか、という唯一解はないのかもしれない。素晴らしい理論に基づいたテーマや、潤沢な予算、個性的な展示空間なども、もちろん魅力です。でも「現代美術」ですから、結局は生きた人間同士で何ができるかという仕事。だから互いの人間性や、その人と協働したいと思えるかどうかが重要になるのでしょう。