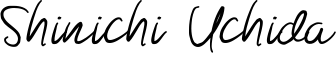CULT VIP:ハービー・ピーカー
取材・文:内田伸一
撮影:佐藤博信
Dazed & confused Japan (27) (2004/06)
Harvey Pekar
1938年、米クリーブランド出身。コミック原作者。自身の日常を描いた『アメリカン・スプレンダー』シリーズで知られる。その半生は同タイトルで映画化され、本人もナレーションおよび一部出演で参加。2003年サンダンス映画祭グランプリなどを獲得した。
※2010年7月に永眠。以下のインタビューは2004年収録です。墓碑銘は"Life is about women, gigs, an' bein' creative."とのこと。ご冥福をお祈りします。
70年代に創刊されたオルタナティブ・コミック『アメリカン・スプレンダー』。クリーブランドで働く事務職員のパッとしない毎日の物語は、原作者で主人公でもあるハービー・ピーカーの実体験そのものだ。しかしその“普通の日々”はなぜか人々を惹き付け、ついに映画板『アメリカン・スプレンダー』まで誕生した。自らも出演したハービーは、その体験自体もネタにするらしい。
「書くネタが尽きることなんてないな……。もしそのとき、つまり物語が終わる日が来るとしたら、それは私の人生が終わるときだ」
こんな発言がキザにも高慢にも聞こえないのは、このハービー・ピーカーという人物が64年の人生で積み上げてきた人徳なのか? あるいは、オルタナティブ・コミック界におけるベテラン原作者としての威厳がそう感じさせる、という見方だってある。どちらも間違いではないだろうが、一番しっくりくる答えは、もう少し単純なところにある。ハービーのネタが尽きないのは、彼のコミックがどれも自分の日常生活をさらけ出したものだからだ。ハービーが執筆した原作を数々の描き手がコミック化する、というかたちで生まれた『アメリカン・スプレンダー』は、1976年の創刊から“大人向けのコミック”(変な意味ではなく)を求める人々を魅了してきた。
スーパーマーケットでレジ前の行列を選ぶとき、どんな人物の後ろに並ぶべきか? あるいは、突然尋ねてきた“たかり癖”のある友人から、逆に1ドルおごってもらうまでのいきさつ。主人公はクリーブランドのサエない労働者、ハービー・ピーカーその人である。そこで描かれるのは、多くの人にとってはコミック化する価値などないように思える出来事ばかりだ。
しかし、そんな日常を綴った『アメリカン・スプレンダー』は、当時のオルタナティブ・コミックシーンにおいて異彩を放ち、徐々に注目されることになる。さらにこのコミックは、ハービーが後に妻として迎える女性、ジョイス・ブラブナーとの出会いのきっかけにもなり(彼女は『アメリカン・スプレンダー』のファンだった)、昨年には彼の半生を描いた同名映画まで生まれることになった。そういうわけで今、ハービーは妻子を連れて、完成した映画と共に各国都市を回っている。この旅自体も、次の作品のネタにしようともくろみながら……。
1939年、ハービー・ピーカーは、オハイオ州クリーブランドに生まれた。少年時代からコミックに親しんできたことは本人も認めるが、ずっとコミック漬けの人生を送ってきたわけではない。成長するにつれジャズや小説に傾倒し(ヘンリー・ミラーが好きらしい)、図書館に入り浸って司書と仲良しになったり、78回転SP盤レコードのコレクションに精を出していた。大学に通った後は、政府関連の退役軍人病院に就職。事務員として働き続ける。ちょっとマニアックな趣味や、2度の離婚などを除けば、ごくごく地味で平凡な人生を送っていた。
そういう彼が33才にしてコミック創作への道を歩み始めたのは、盟友、ロバート・クラムの存在が大きい。子供向けコミックの王道ともいえるスピーキング・アニマルもの(擬人化された動物が主人公のコミック)の体裁をとりながら、内容はとうてい子供向けとは言えない『フリッツ・ザ・キャット』などで知られる名物作家だ(ジャニス・ジョプリンの『チープ・スリル』におけるジャケットワークも彼の有名な作品)。ヒッピー・ムーブメント華やかなりし時代に、コミック界においてカウンターカルチャーを体現したのがクラムの作品だった。
「クラムとは、1962年に初めて出会った。まだアンダーグラウンド・コミックの大きなムーブメントが起こる前のことだ。そのころ彼もクリーブランドに住んでいて、グリーティング・カード用のイラストを描く仕事をしていたよ。それで、『BIG YUM-YUM』という彼の作品を見せてもらって驚いた。いわゆるグラフィック・ノベルと呼ばれるもので、こういうものなら大人向けのコミックとしても成功すると思った。なにしろそれまでのコミックといえば、ヒーローものか、トーキング・アニマルものばかりだったから」
後にロバート・クラムはアンダーグラウンド・コミックの旗手となり、カリフォルニアで活躍している他のコミック作家の作品にも触れるようになる。ハービーいわく「ボヘミアンなライフスタイルを描いていた」こうした作品は、彼がクラムの作品に感じた“大人向けのコミック“への可能性を確信に変えていった。それは単に読み手としての期待ではなく、後に彼自身がコミックの作り手になることにつながっていく。
「彼らの作品は、コミックという表現手段における新しい可能性を強く感じさせた。と同時に、私自分もアーティストになりたい、何か新しいことをしたい、そんなふうに考えるようになっていたと思う」
彼は若い頃から雑誌にジャズの批評を執筆する一面もあり、さらに筋金入りの読書家でもあった。そんなハービーにとって、コミックの筋書き作りというのは、それほど突飛な挑戦ではなかったかもしれない。ただし、ここでひとつ解決すべき課題があった。残念ながら、絵を描く才能はないという事実。ただ、本人にとっては、それも大した問題ではなかったようだ。彼には良き相談相手がいたからである。
「ロバート・クラムが、1972年にサンフランシスコからクリーブランドを訪ねて来てね。それで彼と会ったとき、自分が描いたストーリーボードを見せてみたんだ。棒線で描いた落書きみたいな人物に、セリフ入りの吹き出しを付けておいた。彼はそれを気に入ってくれて、自分が絵を付けてみようと言ってくれたんだ」
1976年、ハービーはクラムらの協力を得て、コミック『アメリカン・スプレンダー』を創刊する。「アメリカの輝き」というちょっと皮肉っぽいタイトル。これが彼と同じくコミックを愛する大人たち、特にアーティストからの共感を呼び、協力を申し出るコミック作家も多く現れ始めた。
「創刊号を見て、カリフォルニア在住のアーティストたち、ロバート・アームストロング、ウィリー・マーフィらが参加を申し出てきた。その後、クリーブランドのコミック作家も加わり、最初は5人くらいだった執筆陣も、確か1年で10人近く増えた。もちろん、お金を払ってのことだよ(笑)」
ただ、玄人受けは良かったといっても、財政的には順風満帆というわけではなかったようだ。『アメリカン・スプレンダー』は90年代にダーク・ホース・パブリッシングに委託するまで、ずっとハービーによる自費出版で発行されていたらしい。

「60〜70年というのはコミックにとってはエキサイティングな時代で、さまざまな才能が登場してきた。自分としてはそのまま大人向けコミックが、従来の子供向けのものよりも広く読まれるくらいになればと思っていたけれど……。あのムーブメントはヒッピーのカウンターカルチャーを反映した部分が大きかった。だからベトナム戦争が終わり、ヒッピーがヤッピーになっていくのと同時に、オルタナティブ・コミックの優れた作品はあまり出てこなくなってしまったんだ。『アメリカン・スプレンダー』を創刊した76年には、アンダーグラウンド・コミックの読者もそんなに多くなかった。だから、これを出版してくれるところもなかったし、出したところで儲からないっていうのが共通の認識のようだった。それなら自分で出すしかない、というわけだ。私はそれまで、ジャズ・レコードのコレクションという趣味に何千ドルものお金を費やしてきた。そのお金を『アメリカン・スプレンダー』に使おうと決めたんだ。どうせ自分のための贅沢に使うなら、同じ金でコミックを作って、それで赤字でも自分が満足できればいいじゃないか、ってね」
ほぼ年1回のペースでシリーズは発行を続け、83年には『アメリカン・スプレンダー』の読者だったジョイス・ブラブナーとの結婚、87年には“American Book Award”を受賞するなど、彼の周辺は、平凡な日常を描くことで逆に賑やかになっていく。80年代にはテレビ番組“Late Night with David Letterman”の名物ゲストに。もっともこれは、政治的発言が理由で降板という、彼にしては珍しく派手な“オチ”がついている(90年代に入ってから2度の再出演はあったようだ)。1990年には癌が発覚するというトラブルがあったが、ハービーはその闘病生活さえも『Our Cancer Year』(我々の癌の年)としてコミック化してしまい、家族に支えられて病気も克服した。
「ハービー・ピーカー自身がいろんな形で登場するのが面白かったよ。子役が演じる少年時代の私、ポール・ジアマッティが演じる、大人になった私、そして私自身も依頼されて出演した。さらに、アニメーション版のハービーも登場する」
そう、いまやさまざまな“ハービー・ピーカー”があちこちに存在している。ただ、こうしてコミックが人気になり、自分自身を離れて何人ものハービーが増殖していくような状況に、躊躇したり戸惑ったりしたことはないのだろうか?
「全然問題ない。ビジネスだからね(笑)。それに、とにかく私は自分の世界しか知らないし、本当に誠実に書けるのはそれだけだから。でもどこかで、自分と同じような人生を多くの人が送っているはずだとも思っている。だからコミックについては、出来上がったものを見てくれれば共感してもらえる、という確信みたいなものは最初からあったと思うよ」
さらに彼は、この映画化にまつわる話もちゃっかり『Our Movie Year』(我々の映画の年)というタイトルで作品化する予定だという。
「その件はちょうどいま動いているところ。もうほとんど脚本はできていて、作家に渡している部分もある。内容は、この映画に参加したこと、またその後にこうやって各都市を回ったことなんかも書いている。サンフランシスコ、ホノルル、日本、オーストラリア、ニュージーランド、アイルランド、イギリス、そんな感じかな。こんなに長い旅に出るのは初めてだけど、家族も一緒だし、いろいろ楽しんでいる」
最後に日本の人々の印象はどうか、と聞いたときの彼の答えは、ハービーがこの世界をどう眺めているかを教えてくれるようでもある。
「行く先々で同じような質問をされるけど、国とか場所とか、そういうもので人をひとくくりに見ることはしないな。どんな人でもひとり一人、それなりに違うものを持っているわけだからね」
取材・文:内田伸一
撮影:佐藤博信
Dazed & confused Japan (27) (2004/06)
Harvey Pekar
1938年、米クリーブランド出身。コミック原作者。自身の日常を描いた『アメリカン・スプレンダー』シリーズで知られる。その半生は同タイトルで映画化され、本人もナレーションおよび一部出演で参加。2003年サンダンス映画祭グランプリなどを獲得した。
※2010年7月に永眠。以下のインタビューは2004年収録です。墓碑銘は"Life is about women, gigs, an' bein' creative."とのこと。ご冥福をお祈りします。
70年代に創刊されたオルタナティブ・コミック『アメリカン・スプレンダー』。クリーブランドで働く事務職員のパッとしない毎日の物語は、原作者で主人公でもあるハービー・ピーカーの実体験そのものだ。しかしその“普通の日々”はなぜか人々を惹き付け、ついに映画板『アメリカン・スプレンダー』まで誕生した。自らも出演したハービーは、その体験自体もネタにするらしい。
「書くネタが尽きることなんてないな……。もしそのとき、つまり物語が終わる日が来るとしたら、それは私の人生が終わるときだ」
こんな発言がキザにも高慢にも聞こえないのは、このハービー・ピーカーという人物が64年の人生で積み上げてきた人徳なのか? あるいは、オルタナティブ・コミック界におけるベテラン原作者としての威厳がそう感じさせる、という見方だってある。どちらも間違いではないだろうが、一番しっくりくる答えは、もう少し単純なところにある。ハービーのネタが尽きないのは、彼のコミックがどれも自分の日常生活をさらけ出したものだからだ。ハービーが執筆した原作を数々の描き手がコミック化する、というかたちで生まれた『アメリカン・スプレンダー』は、1976年の創刊から“大人向けのコミック”(変な意味ではなく)を求める人々を魅了してきた。
 |
| 『アメリカン・スプレンダー』(日本語版はブルースインターアクションズ刊) |
スーパーマーケットでレジ前の行列を選ぶとき、どんな人物の後ろに並ぶべきか? あるいは、突然尋ねてきた“たかり癖”のある友人から、逆に1ドルおごってもらうまでのいきさつ。主人公はクリーブランドのサエない労働者、ハービー・ピーカーその人である。そこで描かれるのは、多くの人にとってはコミック化する価値などないように思える出来事ばかりだ。
しかし、そんな日常を綴った『アメリカン・スプレンダー』は、当時のオルタナティブ・コミックシーンにおいて異彩を放ち、徐々に注目されることになる。さらにこのコミックは、ハービーが後に妻として迎える女性、ジョイス・ブラブナーとの出会いのきっかけにもなり(彼女は『アメリカン・スプレンダー』のファンだった)、昨年には彼の半生を描いた同名映画まで生まれることになった。そういうわけで今、ハービーは妻子を連れて、完成した映画と共に各国都市を回っている。この旅自体も、次の作品のネタにしようともくろみながら……。
 |
 |
| 映画『アメリカン・スプレンダー』より。ポール・ジアマッティがピーカーを演じた |
1939年、ハービー・ピーカーは、オハイオ州クリーブランドに生まれた。少年時代からコミックに親しんできたことは本人も認めるが、ずっとコミック漬けの人生を送ってきたわけではない。成長するにつれジャズや小説に傾倒し(ヘンリー・ミラーが好きらしい)、図書館に入り浸って司書と仲良しになったり、78回転SP盤レコードのコレクションに精を出していた。大学に通った後は、政府関連の退役軍人病院に就職。事務員として働き続ける。ちょっとマニアックな趣味や、2度の離婚などを除けば、ごくごく地味で平凡な人生を送っていた。
そういう彼が33才にしてコミック創作への道を歩み始めたのは、盟友、ロバート・クラムの存在が大きい。子供向けコミックの王道ともいえるスピーキング・アニマルもの(擬人化された動物が主人公のコミック)の体裁をとりながら、内容はとうてい子供向けとは言えない『フリッツ・ザ・キャット』などで知られる名物作家だ(ジャニス・ジョプリンの『チープ・スリル』におけるジャケットワークも彼の有名な作品)。ヒッピー・ムーブメント華やかなりし時代に、コミック界においてカウンターカルチャーを体現したのがクラムの作品だった。
 |
| The Complete Crumb Comics Vol. 8: The Death of Fritz the Cat |
「クラムとは、1962年に初めて出会った。まだアンダーグラウンド・コミックの大きなムーブメントが起こる前のことだ。そのころ彼もクリーブランドに住んでいて、グリーティング・カード用のイラストを描く仕事をしていたよ。それで、『BIG YUM-YUM』という彼の作品を見せてもらって驚いた。いわゆるグラフィック・ノベルと呼ばれるもので、こういうものなら大人向けのコミックとしても成功すると思った。なにしろそれまでのコミックといえば、ヒーローものか、トーキング・アニマルものばかりだったから」
後にロバート・クラムはアンダーグラウンド・コミックの旗手となり、カリフォルニアで活躍している他のコミック作家の作品にも触れるようになる。ハービーいわく「ボヘミアンなライフスタイルを描いていた」こうした作品は、彼がクラムの作品に感じた“大人向けのコミック“への可能性を確信に変えていった。それは単に読み手としての期待ではなく、後に彼自身がコミックの作り手になることにつながっていく。
「彼らの作品は、コミックという表現手段における新しい可能性を強く感じさせた。と同時に、私自分もアーティストになりたい、何か新しいことをしたい、そんなふうに考えるようになっていたと思う」
 |
| 映画『アメリカン・スプレンダー』より |
彼は若い頃から雑誌にジャズの批評を執筆する一面もあり、さらに筋金入りの読書家でもあった。そんなハービーにとって、コミックの筋書き作りというのは、それほど突飛な挑戦ではなかったかもしれない。ただし、ここでひとつ解決すべき課題があった。残念ながら、絵を描く才能はないという事実。ただ、本人にとっては、それも大した問題ではなかったようだ。彼には良き相談相手がいたからである。
「ロバート・クラムが、1972年にサンフランシスコからクリーブランドを訪ねて来てね。それで彼と会ったとき、自分が描いたストーリーボードを見せてみたんだ。棒線で描いた落書きみたいな人物に、セリフ入りの吹き出しを付けておいた。彼はそれを気に入ってくれて、自分が絵を付けてみようと言ってくれたんだ」
1976年、ハービーはクラムらの協力を得て、コミック『アメリカン・スプレンダー』を創刊する。「アメリカの輝き」というちょっと皮肉っぽいタイトル。これが彼と同じくコミックを愛する大人たち、特にアーティストからの共感を呼び、協力を申し出るコミック作家も多く現れ始めた。
「創刊号を見て、カリフォルニア在住のアーティストたち、ロバート・アームストロング、ウィリー・マーフィらが参加を申し出てきた。その後、クリーブランドのコミック作家も加わり、最初は5人くらいだった執筆陣も、確か1年で10人近く増えた。もちろん、お金を払ってのことだよ(笑)」
ただ、玄人受けは良かったといっても、財政的には順風満帆というわけではなかったようだ。『アメリカン・スプレンダー』は90年代にダーク・ホース・パブリッシングに委託するまで、ずっとハービーによる自費出版で発行されていたらしい。

「60〜70年というのはコミックにとってはエキサイティングな時代で、さまざまな才能が登場してきた。自分としてはそのまま大人向けコミックが、従来の子供向けのものよりも広く読まれるくらいになればと思っていたけれど……。あのムーブメントはヒッピーのカウンターカルチャーを反映した部分が大きかった。だからベトナム戦争が終わり、ヒッピーがヤッピーになっていくのと同時に、オルタナティブ・コミックの優れた作品はあまり出てこなくなってしまったんだ。『アメリカン・スプレンダー』を創刊した76年には、アンダーグラウンド・コミックの読者もそんなに多くなかった。だから、これを出版してくれるところもなかったし、出したところで儲からないっていうのが共通の認識のようだった。それなら自分で出すしかない、というわけだ。私はそれまで、ジャズ・レコードのコレクションという趣味に何千ドルものお金を費やしてきた。そのお金を『アメリカン・スプレンダー』に使おうと決めたんだ。どうせ自分のための贅沢に使うなら、同じ金でコミックを作って、それで赤字でも自分が満足できればいいじゃないか、ってね」
 |
| 映画『アメリカン・スプレンダー』より |
ほぼ年1回のペースでシリーズは発行を続け、83年には『アメリカン・スプレンダー』の読者だったジョイス・ブラブナーとの結婚、87年には“American Book Award”を受賞するなど、彼の周辺は、平凡な日常を描くことで逆に賑やかになっていく。80年代にはテレビ番組“Late Night with David Letterman”の名物ゲストに。もっともこれは、政治的発言が理由で降板という、彼にしては珍しく派手な“オチ”がついている(90年代に入ってから2度の再出演はあったようだ)。1990年には癌が発覚するというトラブルがあったが、ハービーはその闘病生活さえも『Our Cancer Year』(我々の癌の年)としてコミック化してしまい、家族に支えられて病気も克服した。
とにかく私は自分の世界しか知らないし、本当に誠実に書けるのはそれだけだから。でもどこかで、自分と同じような人生を多くの人が送っているはずだとも思っている。
1991年には『アメリカン・スプレンダー』が舞台化され、さらに2003年には、映画版『アメリカン・スプレンダー』が完成。ハービー自身も本人として登場するこの作品は、コミックに登場したシーンを多く織り込みつつ、彼の半生を描いたものだ。
 |
 |
| 映画『アメリカン・スプレンダー』より(下写真は本人) |
そう、いまやさまざまな“ハービー・ピーカー”があちこちに存在している。ただ、こうしてコミックが人気になり、自分自身を離れて何人ものハービーが増殖していくような状況に、躊躇したり戸惑ったりしたことはないのだろうか?
「全然問題ない。ビジネスだからね(笑)。それに、とにかく私は自分の世界しか知らないし、本当に誠実に書けるのはそれだけだから。でもどこかで、自分と同じような人生を多くの人が送っているはずだとも思っている。だからコミックについては、出来上がったものを見てくれれば共感してもらえる、という確信みたいなものは最初からあったと思うよ」
さらに彼は、この映画化にまつわる話もちゃっかり『Our Movie Year』(我々の映画の年)というタイトルで作品化する予定だという。
「その件はちょうどいま動いているところ。もうほとんど脚本はできていて、作家に渡している部分もある。内容は、この映画に参加したこと、またその後にこうやって各都市を回ったことなんかも書いている。サンフランシスコ、ホノルル、日本、オーストラリア、ニュージーランド、アイルランド、イギリス、そんな感じかな。こんなに長い旅に出るのは初めてだけど、家族も一緒だし、いろいろ楽しんでいる」
最後に日本の人々の印象はどうか、と聞いたときの彼の答えは、ハービーがこの世界をどう眺めているかを教えてくれるようでもある。
「行く先々で同じような質問をされるけど、国とか場所とか、そういうもので人をひとくくりに見ることはしないな。どんな人でもひとり一人、それなりに違うものを持っているわけだからね」